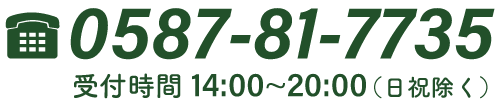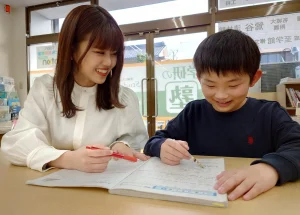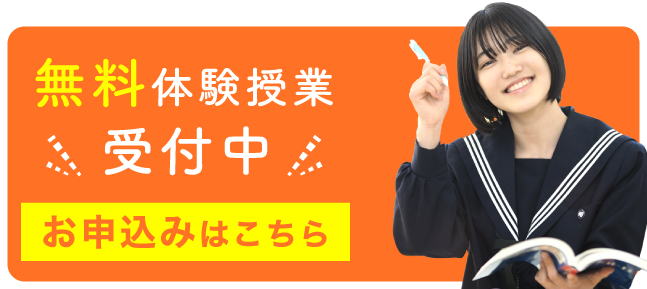こんにちは!自己肯定感カウンセラー・メンタルトレーナーの藤川裕子です。
出産のため、しばらくお休みをいただいていましたが、8月からこちらのコラムにて復帰します。
どうぞ宜しくお願いいたします。
さて、こちらコラムでは、稲沢駅西校にお子さんを通わせている保護者の皆さまへ、 「心の土台を育てること」の大切さと、その具体的な方法をお届けしていきます。
今回のテーマは、「未来を輝かせるカギとなる“自己肯定感”について」。
私たち大人も、そしてもちろん子どもたちも、 毎日を笑顔で、前向きに、しなやかに生きるためには、 「自分って悪くないかも」「やればできるかも」という “小さな自己肯定感”の積み重ねが必要不可欠です。
けれど、日々の生活の中で、こんなお悩みを抱えていませんか?
✓ うちの子、何をしてもすぐに「どうせ無理」と言ってあきらめてしまう ✓ つい怒ってしまい、「また怒っちゃった…」と自己嫌悪になる ✓ ちょっとしたことで落ち込んで、自信を失っている様子が心配 ✓ 学校や塾では頑張っているけれど、家では無気力…
もし、1つでも当てはまるものがあれば、 ぜひ今日のお話を最後まで読んでみてください。
■ 自己肯定感とは?
心理学では「自己肯定感=自分や自分の人生にYESと言える力」 と定義されています。
これは、自分の価値や存在を認める心の土台です。
自己肯定感が高まると、子どもたちは 「間違っても大丈夫」「挑戦してみたい」と思えるようになります。
逆に、自己肯定感が低い状態だと、 どんなに努力しても、「失敗=自分がダメ」と感じてしまい、 行動する前に諦めたり、感情のアップダウンに振り回されてしまいます。
■ なぜ、いま“自己肯定感”が必要なのか?
内閣府の調査によると、 13歳から29歳の若者で「自分に満足している」と答えた人は、わずか7.5%。
なんと、12人に1人しか、自分のことを肯定できていないのです。
そしてこの傾向は、大人になっても続いています。 SNSや成績で比べられる環境の中で、 子どもたちは無意識に「自分は劣っている」と感じてしまうことが多いのです。
だからこそ今、意識的に“心の土台”を育てるサポートが必要です。
■ ご家庭でできる!自己肯定感を育む習慣
では、忙しい毎日の中でもできる「自己肯定感を育む習慣」をご紹介します。
【1】「事実+気持ち」を伝える声かけをする
✕「すごいね!えらい!」 〇「最後までやりきったね。あきらめなかったのが本当に立派だよ」
このように結果ではなく「プロセス」「姿勢」を認めることで、 子どもは「頑張った自分」を好きになっていきます。
【2】1日1つ「できたこと」を一緒に見つける
夜寝る前、「今日のできたこと」を1つ聞いてみましょう。
✓ 授業中に手を挙げられた ✓ 忘れ物をしなかった ✓ 席替えで不安だったけど頑張って友達に話しかけた
など、日常に溢れている些細なことでOKです。 自分で「できた」と感じられることを積み重ねていくと、 脳は“前向きモード”に切り替わっていきます。
【3】親自身も「自分を認める」
子どもにとって、親の姿は“教科書”です。
完璧を求めず、「今日も疲れてるけど頑張ったな、私」 と、ひと言でも自分に声をかけてあげてみてください。
その“自分への優しさ”が、 お子さんに自然と伝わっていき、お子さんの自己肯定感が高まっていきます。 親の自己肯定感が高い家庭で育つ子どもは自己肯定感が高いと言われています。
■ 自己肯定感が育つと、こんな変化が
✓ やる気が続くようになる ✓ 自分のペースで努力できる ✓ 挑戦を楽しめる ✓ 人と比べず、自分の価値を感じられる ✓ 志望校合格など、大きな目標にも前向きに取り組める
まさに、自己肯定感は「前向きに生きるためのエネルギー源」です。
■ おわりに
これからの時代、知識や点数だけでなく、 「自分らしく生きる力」こそが本当の意味での学力だと、私は信じています。
学習塾という学びの場から、 お子さんたちの“心の土台”を育てる一助となれるよう、 メンタルトレーナーとしてできることを、これからお届けしていきます。
次回は、 【自己肯定感がゆらぐ理由と、家庭でできる3つのサポート】をテーマにお送りします!
ぜひ、楽しみにしていてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
藤川裕子(自己肯定感カウンセラー/メンタルトレーナー)